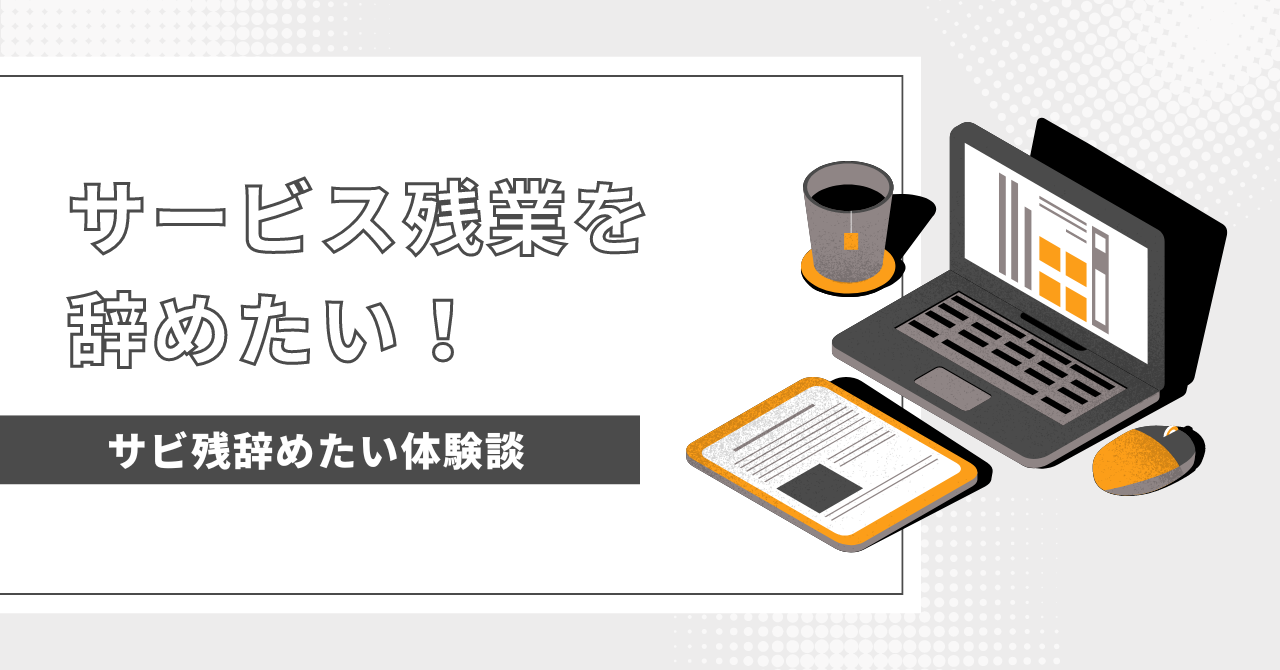
「サービス残業が多い会社を辞めたい」と悩んでいるあなたへ。
気づけば心も体もヘトヘトで、「もう限界だ…」と感じてしまうのも無理はありませんよね。
もしかしたら、
なんて、自分を責めてしまっているかもしれません。
でも、そんな風に思う必要は全くないんですよ。
自分の大切な時間や健康、そして一生懸命な頑張りを守りたい、正当に評価されたいと思うのは、人としてごく自然で当たり前の感情ですから。
この記事では、サービス残業のある会社を辞めたいと感じるのは甘えではないと言える理由と仕事で限界を感じた時の解決策を紹介します。
一緒に、より良い未来への道を探していきましょう。
【体験談】サービス残業が当たり前の会社を辞めたいと悩んでいたプログラマー3年目
あの頃の僕は、都内のIT企業で働く、しがないプログラマー3年目でした。
新卒で入ったその会社は、正直言って、いわゆるブラック企業だったんだと思います。
入社したての頃は、右も左もわからなくて、とにかく必死でした。
「早く一人前になりたい!」
その一心で、多少の無理は気合で乗り切っていたんです。
先輩たちも遅くまで残っているし、それが当たり前なんだろうなって。
でも、2年目、3年目になっても状況は全く変わりませんでした。
いや、むしろ悪化していたかもしれません。
常にプロジェクトは炎上気味で、毎日が繁忙期のよう。
「納期絶対厳守!」の声だけが虚しく響き渡り、僕たちはひたすらコードを書き続ける日々でした。
定時なんてあってないようなもの。
毎日、終電ギリギリまで会社にいるのが当たり前。
タイムカードなんて定時で切らされていました。
「なんでみんなサービス残業してるんだろ…」って、心の中では何度もつぶやいていました。
でも、周りも同じように働いているし、上司に何か言えるような雰囲気でもなくて…。
ただただ、夜遅くまでキーボードを叩き続けていたんです。
原因は、どう考えても人手不足でした。
明らかにキャパオーバーな仕事量を、少ない人数で無理やり回していたんです。
先輩が何度か上司に「人を増やしてほしい」と訴えたこともありました。
でも、返ってくるのは「今は厳しい」「もう少しみんなで頑張ってくれ」という言葉ばかり。
「会社は社員をただの駒としか見ていないんじゃないか…」
そんな疑念が日に日に強くなっていきました。
体力的にも、精神的にも、もう限界が近づいていました。
平日は寝不足で頭がボーッとするし、休日も疲れが抜けきらない。
趣味だったゲームもやる気になれず、ただひたすら寝て過ごすだけ。
「俺、何のために働いてるんだろう…」って、虚しさがこみ上げてきました。
そんなある日、久しぶりに大学時代の友人と会う機会があったんです。
彼は別の業界で働いていたんですが、話を聞いて愕然としました。
「うちは残業代、ちゃんと全額出るよ。最近ボーナスも結構出てさー」
悪気なく話す彼が、なんだかすごく眩しく見えました。
その瞬間、ズシン…と重い何かが僕の心にのしかかってきました。
強烈な劣等感と、自分の置かれている状況への怒り。
「なんで俺は、こんなにボロボロになるまで働いて、残業代もボーナスも出ないんだ…?」
今の会社にいても、給料が上がる見込みはない。
スキルアップだって、日々の業務に追われてままならない。
このままじゃ、ただ時間を浪費して、心と体をすり減らしていくだけだ。
「自分の人生、この会社で終わらせたくない!」
そう強く思ったんです。
もう、この会社にしがみついている理由はない。
そこからは早かったです。すぐに転職活動を始めました。
幸い、IT業界は人手不足なところも多く、僕の3年間の経験でも、いくつかの会社から興味を持ってもらえました。
転職エージェントの方にも親身に相談に乗ってもらい、最終的に、残業管理がしっかりしていて、ちゃんとボーナスも出る会社に転職することができたんです。
退職を伝えるのは少し勇気がいりましたが、「自分の人生のためだ」と言い聞かせて、はっきりと意思を伝えました。
今は、新しい職場でプログラマーとして働いています。
もちろん仕事なので大変なこともありますが、サービス残業とは無縁の環境で、心身ともに健康的に働けています。
あの時、勇気を出して会社を辞める決断をして、本当によかったと心から思っています。
サービス残業のある会社を辞めたいと感じるのは甘えではない
もしかしたら、「辞めたいなんて思うのは、自分が弱いだけなのかな」「甘えているだけなのかな」なんて、自分を責めてしまっているかもしれません。でも、決してそんなことはないんですよ。
ここでは、なぜサービス残業のある会社を辞めたいと感じるのが甘えではないのか、その理由について説明していきますね。
サービス残業は、働く人の権利や健康、そして頑張りを踏みにじる行為です。それに疑問を感じ、「辞めたい」と思うのは、むしろ当然のことなんです。
それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
労働基準法で定められたルールを守っていないから
サービス残業のある会社を辞めたいと思うのは、甘えではありません。なぜなら、サービス残業は労働基準法という国のルールに違反している行為であり、問題は会社側にあるからです。
法律では、会社は従業員を1日8時間、週40時間を超えて働かせる場合、原則として割増賃金(残業代)を支払わなければならないと定められています。サービス残業は、このルールを無視し、従業員に無償で労働を強いることに他なりません。
- タイムカードを定時で打刻させた後、仕事を続けさせる
- 「仕事が終わらないのは能力が低いからだ」などと言って、残業代を申請させない雰囲気を作る
- 明らかに法定時間を超えているのに、記録上は残業していないことにする
これらはすべて、法律で定められた従業員の権利を侵害する行為です。ルールを守らない会社に対して「おかしい」「辞めたい」と感じるのは、人として、そして労働者として当然の感覚であり、決して甘えなどではないのです。
心と体の健康を著しく損なう可能性があるから
サービス残業が常態化している会社を辞めたいと感じるのは、決して甘えではありません。なぜなら、十分な休息が取れない長時間労働は、心と体の健康を深刻なレベルで蝕んでしまう危険があるからです。
私たちの心と体は、休息なしに働き続けるようにはできていません。サービス残業によってプライベートの時間が削られ、睡眠不足や疲労が蓄積していくと、様々な不調が現れ始めます。それは、自分を守るためのSOSサインなのです。
- 常に寝不足で、日中の仕事に集中できずミスが増えてしまう
- 食欲がなくなったり、逆に過食に走ったりする
- 理由もなくイライラしたり、涙もろくなったり、気分の浮き沈みが激しくなる
このような状態が続けば、過労による重大な疾患や、うつ病などの精神疾患につながるリスクも高まります。自分の健康を守るために「このままではいけない」「辞めたい」と感じるのは、非常に健全な自己防衛本能であり、甘えとは全く違う次元の話なのです。
従業員の努力や成果が正当に評価されていないから
サービス残業が横行する会社を辞めたいと思うのは、甘えなんかじゃありません。なぜなら、サービス残業は従業員の頑張りや費やした時間を「タダ働き」として扱い、その努力や成果を正当に評価していないことの表れだからです。
私たちは、自分の時間と労力を提供する対価として、給料という形で報酬を得ています。サービス残業は、この最も基本的な原則を無視し、従業員の貢献をないがしろにする行為です。
- どれだけ遅くまで残って仕事を片付けても、給料は一切変わらない
- むしろ、サービス残業をすることが「当たり前」「美徳」のような風潮がある
- 成果を上げても、それが昇給やボーナスに全く反映されない
自分の頑張りが認められず、正当な対価も支払われない。そんな状況でモチベーションを維持するのは非常に困難ですし、会社に対する不信感が募っていくのも当然です。
「こんな会社のために、これ以上頑張れない」「辞めたい」と感じるのは、自分の働きに対する正当な評価を求める、ごく自然な感情なのです。
サービス残業のある会社を辞めたいと悩んだ時の選択肢
サービス残業が当たり前の会社で、「もう辞めたい…」と悩んでいる時は、本当に苦しいですよね。自分の心と体を守るためにも、現状を変えるための行動を起こすことが大切です。
ここでは、サービス残業のある会社を辞めたいと悩んだ時に考えられる3つの選択肢について説明していきますね。
一人で抱え込まず、これらの選択肢を参考に、ご自身にとってベストな道を探ってみてください。
それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
現状を変えるために社内外のリソースを活用する
まず試してほしいのは、すぐに諦めずに現状を変えるために行動してみることです。なぜなら、会社によっては改善の余地があったり、客観的な意見を聞くことで自分の状況を整理できたりする可能性があるからです。
サービス残業が常態化しているとしても、会社全体がそれを容認しているとは限りません。また、自分一人で悩んでいるよりも、誰かに相談することで精神的な負担が軽くなることもあります。まずは、状況を変えるためのアクションを起こしてみましょう。
- サービス残業の実態(日付、時間、業務内容)を具体的に記録し、証拠を集める。
- 信頼できる社内の先輩や別部署の上司に、現状を相談してみる。
- 人事部や社内に設置されているコンプライアンス窓口に、匿名で相談してみる。
- 社外の友人や家族、同業種の知人に話を聞いてもらい、客観的なアドバイスをもらう。
- 労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談し、法的なアドバイスやあっせん制度について聞く。
これらの行動を通じて、会社側の対応を見極めたり、自分の状況を客観的に把握したりすることができます。すぐに辞めるという結論を出す前に、まずは現状を変えるためのアクションを起こしてみることも一つの有効な手段ですよ。
将来を見据えて転職活動を始める
現状の会社での改善が難しいと感じたり、すでに見切りをつけていたりする場合は、将来を見据えて転職活動を始めることをおすすめします。
なぜなら、サービス残業のない、自分に合った労働環境の会社を見つけることで、心身の健康を取り戻し、キャリアアップや収入アップといったポジティブな未来を描ける可能性が高まるからです。
今の会社に留まり続けることは、貴重な時間と心身をすり減らし続けるリスクを伴います。新しい可能性を探るために、一歩踏み出してみましょう。
特に、現職が忙しくて情報収集や面接のスケジュール調整が難しい場合は、転職エージェントの活用が有効です。キャリア相談から求人紹介、選考対策、条件交渉までサポートしてくれるので、効率的に転職活動を進められますよ。
- これまでの職務経験やスキル、実績などを洗い出し、キャリアの棚卸しを行う。
- 自分が仕事に求めるもの(労働時間、給与、仕事内容、社風など)を明確にする。
- 転職サイトに登録したり、企業の採用ページをチェックしたりして、求人情報を収集する。
- 転職エージェントに複数登録し、キャリアアドバイザーに相談してみる。
- 応募したい企業が見つかったら、履歴書や職務経歴書などの応募書類を作成・準備する。
転職活動は、すぐに結果が出なくても、自分の市場価値を知ったり、キャリアについて考えたりする良い機会になります。今の環境に不満があるなら、より良い未来のために、まずは情報収集からでも始めてみることが大切です。
心身の限界を感じたら退職も視野に入れる
もし、サービス残業によって心や体の健康が明らかに損なわれている、あるいは限界を感じているのであれば、最終手段として退職することも真剣に検討しましょう。なぜなら、あなたの心と体の健康以上に大切なものはないからです。
無理をして働き続けることは、症状を悪化させ、回復までに長い時間がかかってしまう可能性があります。そうなると、その後のキャリアにも影響が出かねません。自分自身を守るために、「辞める」という決断が必要な時もあります。
特に、上司からのプレッシャーが強くて退職を言い出しにくい、あるいは退職交渉がスムーズに進まないといった場合には、退職代行サービスの利用も有効な選択肢です。専門家が間に入ることで、精神的な負担なく、スムーズに退職手続きを進めることができますよ。
- 自分の心と体の状態を最優先に考え、退職の意思を固める。
- 退職希望日を明確に設定し、就業規則に則って退職の意思を伝える(可能であれば退職届を準備)。
- 後任者への引き継ぎ計画を立て、可能な範囲で協力し、円満退職を目指す。
- 有給休暇の残日数を確認し、計画的に消化できるよう会社に申請・相談する。
- どうしても退職を言い出せない、引き止めにあって辞められない場合は、退職代行サービスの利用を検討する。
サービス残業が蔓延る会社から離れることは、決して逃げではありません。自分を守り、新しいスタートを切るための前向きな選択です。限界を感じているなら、勇気を出して退職という選択肢も考えてみてください。
【Q&A】サービス残業が多い会社を辞めたいと悩んだ時の疑問に回答
ここでは、「サービス残業が辛くて会社を辞めたい」と悩んだ時に感じる疑問について、分かりやすく回答していきますね。
それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
サービス残業って、やっぱり違法なんですか?
はい、原則として違法です。
日本の労働基準法では、会社が従業員に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせる場合や、休日労働をさせる場合には、割増賃金(残業代や休日手当)を支払わなければならないと定められています。
タイムカードを定時で打刻させた後に仕事を続けさせる、残業代を申請させない雰囲気を作る、といった行為は、この法律に違反する可能性が高いです。
つまり、サービス残業は、法律で守られているはずの労働者の権利を侵害する行為と言えるでしょう。
サービス残業を理由に会社を辞めるのって、甘えでしょうか?
いいえ、決して甘えではありません。
サービス残業は法律違反の可能性があり、心身の健康を損なうリスクも高いです。
また、自分の時間と労力を無償で提供させられ、努力が正当に評価されない状況は、働くモチベーションを大きく低下させます。
このような状況に対して「おかしい」「辞めたい」と感じるのは、労働者として、また一人の人間として、ごく自然で当然の感情です。
自分の権利や健康を守ろうとすることは、甘えではなく、むしろ健全な自己防衛本能と言えるでしょう。
サービス残業の証拠って、どうやって集めたらいいですか?
サービス残業の証拠を集めるには、客観的な記録を残すことが重要です。
例えば、実際の出退勤時間を記録したタイムカードの写真やコピー、業務日報、パソコンのログイン・ログオフ記録、業務に関するメールの送受信記録(日時がわかるもの)、上司からの残業指示がわかるメールやチャットの記録などが有効です。
可能であれば、毎日手帳などに始業・終業時間、休憩時間、具体的な業務内容をメモしておくことも役立ちます。
ポイントは、「いつ、どれくらいの時間、どんな業務をしていたか」を客観的に示せる記録を、できるだけ多く、継続的に残すことです。
会社に「辞めたい」って、どう切り出せばいいですか?
まずは、会社の就業規則を確認し、退職に関するルール(申し出の時期や方法など)を把握しましょう。
一般的には、直属の上司に「ご相談したいことがあります」とアポイントを取り、二人きりになれる場所で、退職の意思を伝えます。
伝える際は、感情的にならず冷静に、「〇月〇日をもって退職させていただきたいです」と、退職希望日を明確に伝えることが大切です。
理由を聞かれた場合は、「一身上の都合」でも構いませんが、もし差し支えなければ、正直に伝えても良いでしょう。
感謝の気持ちを添えつつ、強い意志を持って伝えることが円満退職のポイントです。
辞めた後、未払いの残業代って請求できますか?
はい、請求できる可能性はあります。
未払いの残業代を請求する権利は、原則として給料日の翌日から3年間有効です(法改正により2年から3年に延長されました)。
請求するには、サービス残業をしていたことを証明する客観的な証拠が重要になります。
退職後であっても、在職中に集めた証拠(タイムカードのコピー、業務日報、PCログなど)があれば、請求手続きを進めやすくなります。
請求方法としては、まず会社に直接請求し、応じない場合は内容証明郵便を送る、労働基準監督署に相談する、弁護士に依頼して交渉や労働審判・訴訟を行うなどの方法が考えられます。
【まとめ】サービス残業が多い会社を辞めたいと悩むあなたへ
サービス残業が続いて「心も体も限界…」と感じるのは、決して甘えではありません。
むしろ、自分の心と体を守ろうとする大切なサインなんです。
サービス残業の証拠を集めて専門家に相談したり、新しい環境を探して転職活動を始めたり、時には思い切って退職したりすることも、あなた自身を守るための立派な一歩です。
一人で抱え込まず、勇気を出して行動すれば、必ず道は開けます。
サービス残業のない、あなたが心から納得できる働き方ができる場所はきっと見つかります。
あなたの未来が、より明るく、あなたらしく輝くものになるよう、心から応援しています。
その一歩が、新しい未来への扉を開きますよ。




